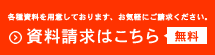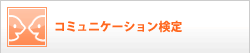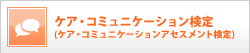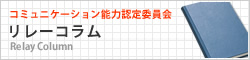スピーチ ―間断なきコミュニケーション線の中で捉えよ
多くの人がスピーチ=演説という特別な分野があり、作法集のごときものを学べばそれは習得できるものと健気にも、また愚かしくも信じ込んでいる。たとえば、「第一声を発する前に、聞き手全体を見回しましょう」「歩きながらの挨拶は行儀が悪いからやめなさい」等である。だが、これなどはどうか。私の関係していた学会で故・大島渚監督がある賞を受賞した時、氏は、「歩きながら」どころではない。奥方で女優の小山明子さんの押す車いすに座りながら、我々の脇を疾風のごとく中央に駆け上がっていった。入場の時からスピーチは始まっていたのである。退場とて、千両役者のように花道を下っていく場合もあれば、マイケルジャクソン式のムーンウォークで下がりながら「ありがとうジャパン!」といって退場することも可能だ。そればかりではない。人は人生舞台に登場するとき、逆子は脚から入場する。そして去る時は「聴衆」に手を合わさせ、仰向けに寝て車で退場する。"天国の淡谷のり子さんが舞い降りてきたスピーチ"なんてのもあった。役所のルールブックではない。仮想世界に思いを馳せ、生きとし生ける者を観察していくことが魅力あるコミュニケーション能力開発の第一歩である。
次に聴衆という存在。彼らはまんじりともせずに話を聞いてくれる学校教師ではない。最後に一人しか残らないのに、もくもくと準備したようにしか話せないのは生きたコミュニケーターではない。壇上から降りて少人数のトークに切り替える柔軟性もほしい。まさか「それはスピーチでなく会話だ」とはいえまい。最後に「いいたいことをもて」などというがこれも厳密には違う。まず目的ありき。たとえばカネの有効活用について説得という目的がある。その目的達成のために、どんな内容をもってくるかは選択項目である。蓋をあけてみて幼稚園児だったら「年金」の話はやめて「お小遣い」にでも切り替えるだろう。
スピーチが日常のコミュニケーションと切り離されたところに鎮座しているのではない。間断なく続くコミュニケーションの線の中で、時に改まり、時にくだけ、聴衆空間の変化に対応できる能力を養っていくことが求められる。そのためにパブリックスピーキング、演劇、朗読(音声解釈表現=オーラルインタープリテーション)、ディベートが一丸となった領域に日本の言語教育が向き合っていくことが求められる。